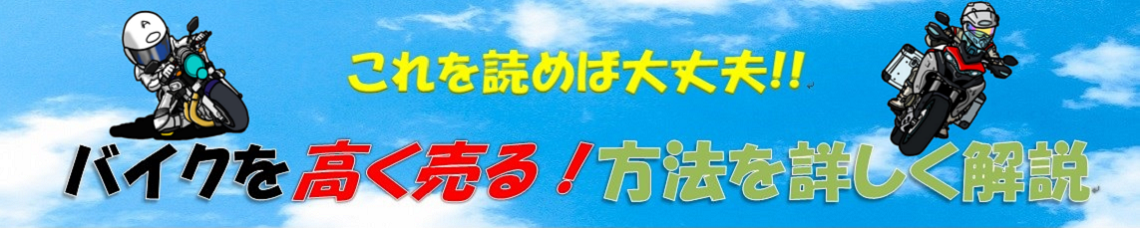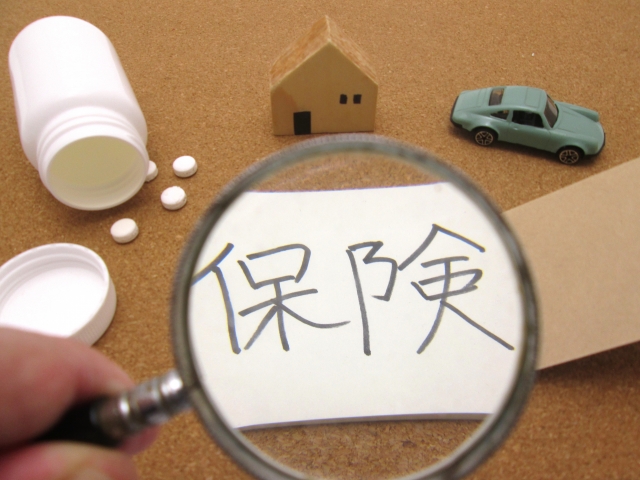
任意保険とは、自賠責保険でカバーできない損害の部分を補償する保険です。
自賠責保険の特徴は
- 事故を起こしても物損事故は、補償対象にならない。
- 後遺障害などがつかない人身事故では、最大120万円しか支払われない。
自賠責保険の保障だけでは、事故の加害者も被害者も、安心できません。
また、交通事故の「損害賠償金」や「慰謝料」に、弁護士特約を利用した弁護士の利用が、簡単にできるようになりました。
そのため、「損害賠償金」や「慰謝料」が高額になり、自賠責保険で全額補填することが難しくなってきています。
一方で任意保険は、高額な損害賠償の支払いに備えられることや、示談交渉を有利にすすめるための特約などのサービスが充実しています。
上記の理由により、現在では任意保険の重要性が高まっています。バイクを運転するときは、任意保険の加入をおすすめします。
なぜ任意保険に加入するべきなのか、5つの理由について詳しく説明します。
1、物損事故には任意保険でしか対応できない
自賠責保険は、事故の被害者を救済することが目的であるため、人身事故のみが対象です。
被害者に怪我がなく、物だけを壊してしまう物損事故には対応していません。
人身事故の賠償額は、とても高額です。たとえば、5億円を超すケースもあります。一方で、物損事故でも、人身事故と同様、賠償金額が高額になる場合があります。そこで、物損事故の補償をするために、任意保険の対物賠償保障が必要になってきます。
では、過去におきた対物事故の高額賠償の例をあげてみます。
| 認定総損害額 | 判決年月日 | 被害物件 |
|---|---|---|
| 2億6,135万円 | 1994年7月19日 | 積荷(呉服・洋服・毛皮) |
| 1億3,580万円 | 1996年7月17日 | 店舗(パチンコ店) |
| 1億2,036万円 | 1980年7月18日 | 電車・線路・家屋 |
参考:日本損害保険協会
上記の対物事故は車での事故ですが、バイクでも対物事故をおこすと、車と同様に賠償額が高額になる場合があります。
バイクに乗っていた加害者が、任意保険の対物賠償保障に入っていない場合、賠償額は全額自分で負担しなければなりません。
2、人身事故の損害賠償額は高額になっている
自賠責保険の死亡による損害賠償の上限は、3,000万円までです。また、後遺障害による損害賠償の最高額は、4000万円までです。
人身事故の損害賠償額で過去に高額賠償額が出た例をあげてみます。
| 認定総損害額 | 判決年月日 | 被害者性年齢 | 被害者職業 | 被害態様 |
|---|---|---|---|---|
| 5億2,853万円 | 2011年11月1日 | 男性 41歳 | 眼科開業医 | 死亡 |
| 3億9,725万円 | 2011年12月27日 | 男性 21歳 | 大学生 | 後遺障害 |
| 3億9,510万円 | 2011年2月18日 | 男性 20歳 | 大学生 | 後遺障害 |
参考:日本損害保険協会
人身事故をおこしてしまうと、高額な損害賠償額になる場合があります。上記のような損害賠償額の認定が出た場合、自賠責保険の上限金額だけではとてもカバーできない金額です。人身事故を起こしてしまうことを想定すると、任意保険の対人賠償保障額を、無制限にしておく必要があります。
損害賠償額が高額になる理由
上記のように、高額な損害賠償額になる理由は、被害者の年齢や収入、被害の程度で賠償金額が変わってくるからです。では、賠償金額のなかの、治療費と逸失利益についての、計算方法をみてみます。
治療費
交通事故の治療でも健康保険は適用されます。しかし、病院によっては「交通事故は、自由診療しか受けられない」などと言うところがあり、自由診療でおこなわれることが多いです。
なぜなら、病院は自由診療で治療を受けてもらうほうが、病院側の利益が多くなる治療や処置ができ、高い治療費を請求できるからです。
交通事故の加害者になってしまった場合、任意保険の対人賠償保険が「無制限」の補償契約であれば問題ありません。しかし、対人賠償保険が制限付きであれば、契約金額を超えた分は自費になります。
病院の自由診療では、治療費が高額になることがあります。そのため、対人賠償保険を制限付きで加入している場合は、「病院での治療は、健康保険診療で治療してほしい」と、被害者の方へお願いするのも良いでしょう。
高額な治療費を実費で払うことは大変なため、任意保険の対人賠償保険に加入する場合は、「無制限」タイプをおすすめします。
逸失利益
逸失利益とは、原則67歳までの就労可能年数で、事故が無ければ得られるはずの利益のことです。逸失利益を計算するのは、ライプニッツ係数(中間利息)を用いるのが一般的です。
※ライプニッツ係数:中間利息控除ともいう、交通事故の被害にあわなければ得られていた収入と仕事を休んでいた期間の損害を補てんする休業補償などの、損害賠償を前倒しで受け取る際に控除する指数。参考:国土交通省hp 就労可能年数に対するライプニッツ係数表
被害者が、死亡の場合と、後遺障害の場合では、計算方法が違います。計算方法は以下のとおりです。
死亡逸失利益の計算方法
被害者が、50歳会社員で、年収800万円、生活費控除30%、ライプニッツ係数11.274の場合の死亡逸失利益は以下のようになります。
800万円×(1-0.3)×11.274=6,313万4,400円
この計算でもわかるように、賠償額は、自賠責保険の、死亡による慰謝料の限度額3000万円を超えます。自賠責保険で支払われる3000万円を超えた金額は、加害者の負担になります。
後遺障害の逸失利益の計算方法
被害者が、25歳会社員で、年収400万円、後遺障害等級13級に該当する場合の後遺障害の逸失利益は以下のようになります。
400万円×0.09×17.423=627万2,280円
後遺障害の場合、たとえば、後遺障害等級13等級で、任意保険基準の57万円しか支払われません。この場合も、超えた金額は、加害者の負担になります。
3、被害者に対する、慰謝料はいくらになるのか
慰謝料とは、上記の治療費+逸失利益に精神的苦痛に対する慰謝料を含めたものを、一般的に慰謝料といいます。
本来、慰謝料とは、精神的な苦痛に対しての賠償金を指すものです。しかし、入通院慰謝料(治療費含む)と、後遺障害慰謝料または死亡慰謝料など、その他かかった費用を含めた賠償金のことを「交通事故の慰謝料」と表現することがあります。
保険会社によっては、「精神的な苦痛に対しての賠償金のみを慰謝料」とすることがあるため、その場合、治療費などは含まれないことになります。
精神的苦痛に対する慰謝料が発生するのは、人身事故の場合のみです。物損事故に対しては支払われません。そのため、被害者が大切にしていたものが壊れても、壊れたものに対しての慰謝料の支払いは発生しません。
慰謝料の計算方法は、3種類あります。自賠責保険基準と、任意保険基準それに、弁護士(裁判所)基準、の3種類です。これからこの3種類を説明します。
自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、法律で加入が義務付けられている自賠責保険の計算基準です。
死亡事故の場合、自賠責基準では、残された遺族への慰謝料と、葬儀費用が対象になります。計算方法は、以下のようになります。
- 本人への慰謝料:350万円
- 遺族への慰謝料:請求者一人550万円、請求者二人650万円、請求者三人750万円
※遺族とは、被害者の父母、配偶者、子供。被扶養者がいる場合は、200万円加算されます。
- 葬儀費用:60万円
上記を足したものが、慰謝料として計算されます。たとえば、被害者死亡で、遺族が奥さんと学生の子供が一人の場合、350万円+650万円+200万円+60万円=1,265万円が自賠責基準慰謝料となります。
後遺障害の場合の、自賠責保険基準の慰謝料相場を、別表にしました。賠償額は、後遺障害の認定等級により、金額が違います。
また、後遺障害等級認定のなかで一番等級の低い14等級の認定条件は以下のとおりです。
参照:国土交通省hp 後遺障害の等級及び限度額
上記の9つの条件のうち、1つでも当てはまれば後遺障害14等級の認定が受けられます。また、認定される等級により慰謝料相場は変わります。
任意保険基準
各保険会社がいろいろな条件の保険商品を出しています。しかし、任意保険基準の計算基準は明らかにしておりません。ただ慰謝料は、自賠責基準よりも高く提示されているようです。
弁護士(裁判)基準
3種類の基準のなかで、一番高い慰謝料基準になるのが弁護士基準です。弁護士基準の慰謝料は、過去におきた交通事故の裁判判例を基準にしたものだからです。そのため、弁護士基準は、新しい判例が出れば書き換えらます。つまり、弁護士基準による慰謝料の計算方法や金額は、毎年変わるのです。
弁護士基準の慰謝料は、通称「赤い本」といわれる「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」と、通称「青い本」といわれる「交通事故損害額算定基準」を参考に、算定されます。では、被害者が死亡した場合と、後遺障害が残った場合の慰謝料の相場をあげてみます。
被害者が死亡した場合の慰謝料相場
*任意保険基準の金額は推定
| 被害者の立場 | 一家の柱 | 配偶者 | 子供 | 高齢者 |
| 自賠責保険基準 | 350万円 | 350万円 | 350万円 | 350万円 |
| 任意保険基準 | 1500万円~2000万円 | 1300万円~1600万円 | 1200万円~1500万円 | 1100万円~1400万円 |
| 弁護士基準 | 2800万円~3600万円 | 2000万円~3200万円 | 1800万円~2600万円 | 1800万円~2400万円 |
この表からわかるように、被害者が死亡した場合、弁護士基準での慰謝料が、高額になります。
被害者が後遺障害認定された場合の慰謝料相場
*任意保険基準の金額は推定
| 等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
| 第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
| 第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2370万円 |
| 第3級 | 829万円 | 1100万円 | 1990万円 |
| 第4級 | 712万円 | 900万円 | 1670万円 |
| 第5級 | 599万円 | 750万円 | 1400万円 |
| 第6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
| 第7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
| 第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
| 第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
| 第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
| 第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
| 第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害認定の場合でも、弁護士基準が高額になります。弁護士基準を適用するためには、弁護士に依頼する必要があります。任意保険の「弁護士費用特約」に入っていれば、弁護士に依頼できます。その場合の弁護士費用は、保険会社が負担します。
4、任意保険でも保険会社が示談代行できない事故がある
任意保険に入る理由の一つに、事故にあったとき自分で示談交渉するのではなく、保険加入者のかわりに、保険会社が相手と示談交渉する「事故解決サービス」があることがあげられます。しかし、「事故解決サービス」が利用できない事故があります。保険加入者が、以下のような交通事故の被害にあった場合がそうです。
過失割合10対0のもらい事故
任意保険に加入していても、以下のような事故の場合、被害者の保険会社は加害者との示談交渉ができません。
- 停車中に追突された場合
- 相手がセンターラインをオーバーしてきて衝突された場合
- 相手が信号無視で衝突された場合
このような場合は、被害者の過失割合が「0」になります。では、なぜ過失割合が「0」の場合は、保険会社が加害者との示談交渉ができないのでしょうか? それは、弁護士法72条に関係します。
弁護士法第72条とは
示談交渉できない理由は、弁護士法第72条に「弁護士以外の者が報酬を得る目的のために法律事務ができない」と定められているからです。
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
保険会社は、示談代行サービスを保険に付属して販売をし報酬を得るため、被害者の過失割合が「0」の場合報酬が発生しません。そのため保険会社は、法律関係において被害者との関係が他人となってしまい、示談交渉を代理でおこなうことができません。ですので、示談交渉は、全て自分でおこなわなければなりません。
被害者の過失割合が「0」の場合、慰謝料は、加害者が加入している保険会社が100%出してくれます。しかし、提示額に納得がいかない場合は、自分で訴訟費用を出し、全て自分でやらなければなりません。
このような場合、任意保険の弁護士費用特約に加入しておけば、弁護士に加害者との示談交渉をしてもらえます。
弁護士費用特約
任意保険にはいろいろな特約があります。弁護士費用特約も、付帯しておきたい特約のひとつです。弁護士費用特約には、2つの費用が補償されます。
- 弁護士費用:弁護士報酬・訴訟費用・調停にかかる費用を限度額300万円まで支払うもの
- 法律相談費用:弁護士相談費用で限度額10万円まで支払うもの
また、弁護士費用特約では、過失割合「0」のもらい事故だけでなく、他の事故にも対応しています。例をいくつか出してみます。
- 物損事故で加害者が、修理費を払わない
- 加害者が、任意保険に未加入だった
- 相手の保険会社との示談交渉が、うまくすすまず不利になりそう
- 事故の過失割合に、納得ができない
このように、弁護士費用特約に加入していれば、保険会社が示談交渉できない場合に対応してもらえます。また、過失割合「0」で、弁護士費用特約を利用しても次年度のノンフリート等級は、無事故としてカウントされます。
*ノンフリート等級とは、契約期間中の事故の有無や形態により、1等級から20等級まで区分わけしている等級です。等級に応じて保険料が割増、または割引されます。
5、バイク保険特約を知って自分を守ろう
バイク保険には、弁護士費用特約のほかにも、保険会社によって、さまざまな種類の特約があります。その中からお得な特約を紹介します。
◇他社運転特約
他社運転特約とは、借りたバイクで事故をおこしても、自分の任意保険契約の内容に従い保障してくれる特約です。日常的ではなく、一時的に借りたバイクに限定されます。
◇無保険車障害特約
無保険車障害特約とは、保険に入っていないなどの車両との事故で、相手方から十分な補償が得られないときのための保障特約です。
△ファミリーバイク特約(自動車保険に付けることのできる特約)
自動車の任意保険に加入している場合、原付及び原付2種(125cc以下)のバイクであれば、ファミリーバイク特約に加入できます。
ファミリーバイク特約の良いところは、
- 自動車保険の対人賠償、対物賠償、と同じ補償になるところ
- 年齢制限なしでバイク何台でも適応
- バイクで事故をおこしても、自動車保険のノンフリート等級には関係なし
- 借りた原付及び原付2種にも適応されます。
バイクを売ったときには、保険を中断できる
バイクを手放す時、任意保険を中断することができます。ただし、中断にも条件があり、再契約にも条件があります。
中断条件
- 解約日及び満期日までに返還手続きが完了していること
- 解約日及び満期日までに車検証の有効期限が切れていること
- 中断時点での等級が7等級以上であること
再契約条件
- 中断日から再契約日が中断期間内であること
- 新しい車を納車してから1年以内の加入であること
- 中断制度前後の被保険者が同一であること
参考:チューリッヒ保険会社
注意することは、バイクに乗らないだけでは任意保険を中断することができないことです。中断証明書の発行が依頼できるのは、売却後か車検切れ後です。また、中断にも期限があり、中断証明発行の翌日から10年間が有効期限です。
まとめ
このページでは、バイクの任意保険の必要性についてお伝えしてきました。
事故は、加害者になっても被害者になっても大変なことばかりです。任意保険が、必要になるときなど来ないほうがいいです。
しかし、万が一のために任意保険の備えをする必要があることは、このページで理解していただいたと思います。
保険特約などは、きちんと入っていますか? この機会に見直してください。
無事故でバイクライフをおくることがいちばん望ましいことです、もし被害者になったり加害者になってしまったときに、あわてないように保険を見直してください。
保険を見直すならこちらがおすすめです。
また、大事にしてきたバイクを売るとき、任意保険は中断することができます。
次のバイクが決まるまでのあいだ任意保険は中断にしておき、ノンフリート等級をそのまま保留し、次のバイクでまた素敵なバイクライフを送りましょう。

![電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]](http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/EGOV/images/head_logo.jpg)